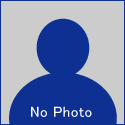|
|
奈良 寧
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
学内職務経歴 【 表示 / 非表示 】
-
国際教養大学 国際教養学部 基盤教育 数学・自然科学,教授,2013/04 ~ 2021/03
-
国際教養大学 国際教養学部 グローバル・コネクティビティ領域,教授,2021/04 ~ 継続中
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Optimal collision energy for realizing macroscopic high baryon-density matter,Physical Review C,112巻 1号 (頁 L011901-1 ~ L011901-7) ,2025/07,H. Taya, A. Jinno, M. Kitazawa, Y. Nara
DOI:doi:10.1103/rpxm-fql8,研究論文(学術雑誌),共著,英語
-
Simultaneous description of high density QCD matter in heavy ion collisions and neutron star observations,Physics Letter B,867巻 (頁 139605-1 ~ 139605-8) ,2025/05,J. Steinheimer, M. Omana Kuttan, T. Reichert, Y. Nara, M. Bleicher
DOI:doi:10.1016/j.physletb.2025.139605,研究論文(学術雑誌),共著,英語
-
Momentum dependent potentials from a parity doubling CMF model in UrQMD: Results on flow and particle production,Journal of Physics G,52巻 3号 (頁 035103-1 ~ 035103-23) ,2025/01,J. Steinheimer, T. Reichert, Y. Nara, M. Bleicher
DOI:doi:10.1088/1361-6471/adab0b,研究論文(学術雑誌),共著,英語
-
Comparing pion production in transport simulations of heavy- ion collisions at 270AMeV under controlled conditions,Physical Review C,109巻 4号 (頁 044609-1 ~ 044609-34-8) ,2024/04,Jun Xu, et. al
DOI:doi:10.1103/PhysRevC.109.044609,研究論文(学術雑誌),共著,英語
-
Bulk properties of the system formed in U+U collisions at sNN=2.12 GeV using the jet AA microscopic transport model,Physical Review C,109巻 5号 (頁 054902-1 ~ 054902-8) ,2024/03,A. K. Sahoo, X. He, Y. Nara and S. Singha
DOI:doi:10.1103/PhysRevC.109.054902,研究論文(学術雑誌),共著,英語
著書 【 表示 / 非表示 】
学術関係受賞 【 表示 / 非表示 】
-
Physical Review C editors' Suggestion,2020/08/19,アメリカ合衆国,学会誌・学術雑誌による顕彰,American Physical Society,Yasushi Nara, Tomoyuki Maruyama, Horst Stoecker
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
基盤研究(C),2025/04 ~ 2028/03,カイラル対称性の効果を取り入れた微視的輸送模型による高密度物質の相構造の研究
-
基盤研究(C),2021/04 ~ 2024/03,量子分子流体力学シミュレーションによる高密度QCD物質の相転移現象の解明
-
基盤研究(B),2017/04 ~ 2020/03,高エネルギー原子核衝突反応の統合模型の構築とQGP物性物理
-
基盤研究(C),2017/04 ~ 2020/03,高エネルギー原子核衝突のための微視的輸送理論によるイベントジェネレータの開発
-
基盤研究(C),2015/04 ~ 2018/03,宇宙線と星間ガスや大気の相互作用終状態を広帯域で再現するシミュレータの開発
研究発表 【 表示 / 非表示 】
-
日本物理学会 2025年 春季大会 ,国内会議,2025/03,オンライン,相対論的量子分子動力学の新しい定式化II,口頭(一般)
-
STAR Collaboration Meeting: eTOF and BES-II workshop,国際会議,2024/12,Brookhaven National Laboratory,A new RQMD formulation: Potentials/EoS in the microscopic transport model JAM,口頭(一般)
-
Workshop 高エネルギー原子核衝突反応で見る原子核の 形状,国内会議,2024/09,理化学研究所,Dynamics of nuclear collisions from microscopic transport models,口頭(一般)
-
日本物理学会 第79回年次大会 2024年,国内会議,2024/09,北海道大学,相対論的量子分子動力学の新しい定式化,口頭(一般)
-
日本物理学会 2024年春季次大会,国内会議,2024/03,オンライン,カイラル対称性の回復の効果を取り入れた相対論的量子分子動力学 による側方フローの解析,口頭(一般)
担当授業科目 【 表示 / 非表示 】
-
2025年度,秋学期,PHY105-2_F,物理実験
-
2025年度,秋学期,PHY105-1_F,物理実験
-
2025年度,秋学期,CPS490-12_F,総合セミナー: AILA IV
-
2025年度,秋学期,PHY100-1_F,物理学入門
-
2025年度,秋学期,GCI198-1_F,グローバル・コネクティビティ自主研究
学外の社会活動 【 表示 / 非表示 】
-
2021年度 国際教養大学 公開講座,2022/01
自然界で物質は、温度や密度により、個体、液体、気体とその状態が変わる。さらに温度が数千度になると、原子が壊れたプラズマ状態(電子とイオン)になる。例えば、太陽はプラズマ状態である。 では、もっと温度あるいは密度を上げていくと、物質はどうなるのだろうか?
ビックバン宇宙論によれば、我々の宇宙は今から 138 億年前にビックバンと呼ばれる一種の爆発から生まれたとされる。 宇宙創成直後は、宇宙での最高温度が達成されたと考えられている。一方、現在の宇宙にはブラックホールや中性子星などの高密度星(コンパクト星)が存在する。中性子星は太陽の質量ぐらいであるが、その半径は 12km 程度であり、中性子星中心部では、現在の宇宙における最高密度状態が達成されていると考えられている。最近は、中性子星同士の衝突によって発生した重力波を観測することにより、中性子内部の情報を探る新しい道具ができた。
このような物資の極限状態は加速器を使った方法で実験室で作り出すことができる。原子核同士を光速に近い速度まで加速させ衝突させる重イオン衝突実験により、 地球上で高温高密物質が生成されるのである。重イオン衝突実験は、4 兆度の超高温状態を実現し、宇宙創成時と同じ状態を生成したり、中性子星中心部以上の超高密度物質を地上の実験で生成する唯一の手段である。
本講義では、高エネルギー重イオン衝突を用い、宇宙最高温度と宇宙最高密度の状態を作りだす実験から、物資の究極の性質が現在どこまでわかったのかを紹介する。